2024年4月号【No.140】(2024年4月15日発行)
2024年4月号【No.140】(2024年4月15日発行)<全体版>
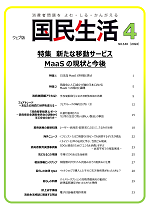
- ※利用しているインターネット環境により時間がかかる場合があります。
- ※アクセスが集中した場合、エラー画面が表示されることがあります。時間をおいてから、再度お試しください。
2024年4月号【No.140】(2024年4月15日発行)<分割版>
特集 新たな移動サービスMaaSの現状と今後
- 1 日本産MaaSの特徴と現状[PDF形式](691KB)
【執筆者】牧村 和彦(一般財団法人計量計画研究所 理事、東京大学博士(工学)、神戸大学 客員教授) - 2 高齢化と人口減少が進む日本におけるMaaSへの期待と課題[PDF形式](357KB)
【執筆者】坊 美生子(株式会社ニッセイ基礎研究所 生活研究部 准主任研究員)
わが国では、運転手の減少等によるバスやタクシーといった公共交通機関の不足や廃止、高齢者の移動手段の確保や交通空白地域の解消などが、主に地方部において課題となっています。それらを解決し、交通手段の維持や確保のために、日本版MaaS(Mobility as a Service:出発地から目的地までの移動を1つのサービスとして提供するしくみ)が活用され始めています。さらに、観光客の導線確保への活用のほか、都市部での渋滞解消などにおいても注目されています。
日本版MaaSについて、そのしくみや特徴、消費者が受けられるサービス内容やメリットなどを解説し、併せて地域での取組事例も紹介します。
消費者問題アラカルト
- 学校制服取引における競争政策の効果[PDF形式](581KB)
【執筆者】石黒 透(公正取引委員会 事務総局 官房総務課長補佐)
フェアトレード−あなたの消費で世界を変える−
- 最終回 フェアトレードの輪を広げる(2)[PDF形式](1MB)
【執筆者】渡辺 龍也(東京経済大学 名誉教授)
「消費者事故調」レポート−消費者安全調査委員会の活動から学ぶ安全のあり方−
- 第3回 共創が重視される「日常の生活で用いる新しい製品」の事故[PDF形式](519KB)
【執筆者】水流 聡子(東京大学 総括プロジェクト機構・大学院工学系研究科 特任教授)
美容医療の基礎知識
- 第6回 レーザー・高周波・超音波によるシミ、たるみの治療[PDF形式](757KB)
【執筆者】石川 浩一(公益社団法人日本美容医療協会 理事)
海外ニュース
- 海外ニュース(2024年4月号)[PDF形式](269KB)
- [フランス]たばこ用香り付きビーズを誤飲する子どもが続出
- [ドイツ]日本の伝統に学ぶ、包装ごみ削減
消費者教育実践事例集
- 第119回 SDGs達成のために「エシカル消費」を学ぶ−高等学校での授業実践−[PDF形式](609KB)
【執筆者】青﨑 孔(長崎県消費生活センター 消費者教育推進員)
気になるこの用語
- 第66回 市場リスクのある生命保険[PDF形式](762KB)
【執筆者】宇田川 俊秀(一般社団法人生命保険協会 理事)
相談情報ピックアップ
- 第57回 樹脂製の折りたたみ式踏み台での指挟みに注意[PDF形式](439KB)
【執筆者】国民生活センター
暮らしの法律Q&A
- ペットショップで購入した子犬に先天性疾患があったときは?[PDF形式](215KB)
【執筆者】小島 直樹(弁護士)
暮らしの判例
- バイナリーオプションの攻略情報商材の勧誘に説明義務違反があったとされた事例[PDF形式](633KB)
【執筆者】国民生活センター 消費者判例情報評価委員会
誌上法学講座
- 【消費生活相談に関連する刑法】第4回 電子計算機使用詐欺罪[PDF形式](783KB)
【執筆者】穴沢 大輔(明治学院大学 法学部 消費情報環境法学科 教授)
啓発用リーフレット(改訂版を作成しました)
- 【改訂版】STOP安易な契約 SNSやネットで見つけたもうけ話[PDF形式](973KB)
【編集・企画】国民生活センター - 【改訂版】ポチッとする前によーくチェックだワン
【編集・企画】国民生活センター
好評いただいております、2020年度と2021年度に作成したリーフレットの内容を更新しました。
引き続きご活用ください!
注意事項
ご使用の際は、次の注意事項をよく読んでお使いください。
ウェブ版「国民生活」に掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は著作権の対象となっています。また、ウェブ版「国民生活」トップページおよび各誌面も、編集著作物として著作権の対象となっており、ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されています。これらの掲載物につき、許可なく変更、改変することを禁じます。
ウェブ版「国民生活」の内容の全部または一部について、国民生活センターの許可なく複製等することは禁止しています。ただし、同法で認められている私的使用のための複製、引用等を禁止するものではありません。
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について


